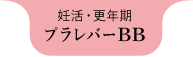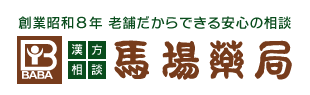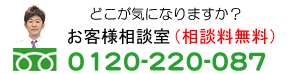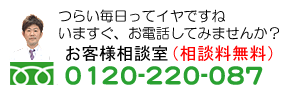肝というと現代では、肝臓だけをさしますが、漢方ではもっと広く自律神経や中枢神経の働き、血液の循環調節など、幅ひろくさしています。
◆肝の性質を知るために、まず 肝に関する漢方の言葉に触れてみませんか。
中国の漢方の古典である「素問」に五行説というものが書かれています。ここでは各臓腑の相互関係と、病気の素因となりうる関係を図表してみました。ただし、すべてがこの表に当てはまるわけでなくいろいろな原因が絡んでいますので、目安として頂けたらと思います。
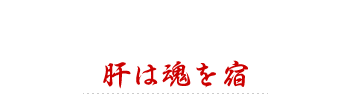
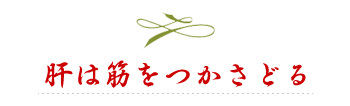
手足が自由に動くのは、筋肉が収縮、伸張するからで、これは肝が正常なら円滑に動くが、肝に異常があると手足がしびれる、ピクピク動く、痙攣する、だるいなどの症状を起こす。

目がよく見えるのは血の巡りがよく、栄養素が豊富に運ばれてくるからだし、レンズの遠近調節や目に入る光量の調節は自律神経によって行われている。だから肝の働きが良くなれば目がよく見えます。

高血圧、目が充血する、いらいらして眠れない、これらも肝の病で、悩み事や受験勉強などで頭を使うと頭に血が上って充血し興奮して眠れない。肝の働きを良くし血液が四肢末端にも不足なく流れるように循環を良くしてやると眠れるようになります。
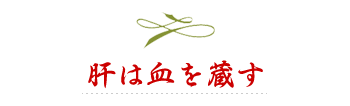
こうなると皮膚がカサカサしてくる、年をとった人には湿疹が出ているわけでもないのに、夜ふとんに入って体が温まると痒くなる老人性ソウヨウ症が多い。
これらは体から水分が抜けて、皮膚がカサカサし、熱をもつために、かゆくなるもので(虚熱)現代医学ではなかなか治りませんが、体をうるおすものを与えると治りやすいのです。
体が血の供給不足のために全体的にひからびてくると、目が乾燥して痒くなったり、かすんだりする。
また、疲れやすくなったり、あたまに血が不足してボーッとしたり顔色が悪く、つやがなくなったり、四肢がしびれたりします。
心臓は血の不足を補うために早く鼓動するから動悸がおこります。
これらはみな、血の滋潤、栄養の衰えによるものです。

この怒りは単に怒ることだけではなく、喜び、悲しみ、憂い、悩みなど心のストレス全般をさしています。
これが長く続くと肝の働きに異常をきたすのです。
また、色では青色が肝と関係し、青っぽい顔色の人には、肝の症状があらわれるとされます。「青筋を立てる」などの言葉は典型的ですね。