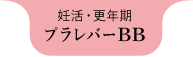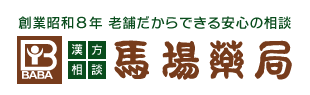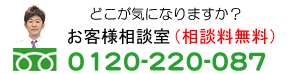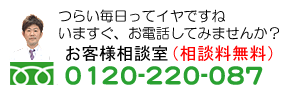二十四節気
今回は「二十四節気(にじゅうよんせっき)」に関連のある事柄について紹介したいと思います。
立春・雨水・啓蟄・春分・清明・穀雨・立夏・小満・芒種・夏至
小暑・大暑・立秋・処暑・白露・秋分・寒露・霜降・立冬・小雪
大雪・冬至・小寒・大寒
二十四節気とは、節分を基準に1年を24等分して約15日ごとに分けた季節のことで、1ヶ月の前半を「節」、後半を「中」と言います。その区分点となる日に季節を表すのにふさわしい春・夏・秋・冬などの名称を付けました。
太陽の運行を元に
古代中国では、月の満ち欠けに基づいた太陰暦が使われていました。しかし太陰暦による日付は、太陽の位置と無関係なため暦と季節の間にズレが生じてしまいました。そこで本来の季節を知る目安として、太陽の運行を元にした二十四節気が暦に導入されました。二十四節気につけられた個々の名前は、その季節の特徴を言い当てているものが多数あります。例えば、3月6日頃の「啓蟄〔けいちつ〕」は「春になって虫が穴から出てくる」という意味です。これらの名前は中国から伝わってきたため、日本の季節とは若干ズレが生じています。
2600年の歴史
二十四節気は太陰暦のような、気候と暦のずれはありません。しかし本来は約2600年前の中国の黄河地方の気候に基づき作られた暦であるため、実際の日本の気候とは多少のずれが生じます。ですが、毎年同じ時期に同じ節気がくることや節気の感覚が約15日で一定しており、半月ごとの季節変化に対応出来ることなどから、農業の目安としては非常に便利であり、日本に導入されるようになりました。
1844年に最新の天文学の知識による改良を加え、1年を太陽の黄道上の位置によって春分点から15度ずつ移った点を区分点と改めました。これにより、暦と季節のズレは多少改善されましたが、太陽の軌道が正円では無いことから、この方法だけでは運行速度の遅速が生じるため「閏年〔うるうどし〕」を設けてズレを調整しています。
日本では1873年に太陰暦から太陽暦に改暦されましたが、現在でもカレンダーの日付の横に二十四節気が記載されていることがあります。
二十四節気と現在
二十四節気は馴染みが無いようにみえて、私たちの日常生活と意外に密接な関係にあります。例えば立春の時には「暦の上では春ですが、まだ風も冷たく」などの時候の挨拶を述べたりすることに始まり、暑い盛りの挨拶「暑中見舞」を立秋以後は暑さの残る季節の挨拶「残暑見舞」に変えることなどが挙げられます。私たちは無意識に日常生活のあらゆる場面において、二十四節気と接しています。
立春
立春は、冬至と春分の間の2月4日頃に当たります。また、この日から雨水(2月19日頃)までの期間を立春と呼ぶこともあります。立春は冬と春の分かれる節目の日である「節分」の翌日で「寒さがあけて春に入る日」いわば春の初日です。
一年の始まりは立春から
旧暦では一年のはじまりは立春からと考えられていたため、立春を基準に様々な決まりや節目の日が存在しています。
春…立春から立夏の前日までを言います。冬至と春分の中間にあたります。この頃、暖かい地方では梅の花が咲き始めます。
■節分…立春の前日のことです。立春が正月なのに対して、大晦日の役割を持ち、一年間
の厄払いのために豆まきを行います。
■八十八夜…立春から数えて88日目のことです。この日に摘んだお茶の葉は霜をかぶらな
いため、高級な茶葉であると言われています。
■二百十日…立春から数えて210日目のことです。この日は台風が襲来する可能性が高く、
農家の人々にとっては厄日だと言われています。
■二百二十日…立春から220日目のことです。二百十日と同じく、台風が襲来する可能性
の高い日とされています。現在は二百十日よりも二百二十日に台風が来ることのほうが多いようです。
立春と正月
古来は、自然の景色の変化から季節の移り変りを把握する「自然暦」を使用していました。飛鳥時代に中国から二十四節気が伝えられると、冬至が年の分割の起点と考えるようになり、立春を一年の初めとして暦が作成されるようになりました。
明治時代に改暦が行われるまでは、立春は正月とほぼ同じ頃に重なっていたため、現代でも正月に「早春」や「新春」といいます。
「立春大吉」で厄祓い
立春の早朝、禅寺では厄除けのために門に「立春大吉」と書いた紙を貼る習慣があります。この文字は、縦書きすると左右対称になり一年間災難にあわないというおまじないです。
また、立春以降に初めて吹く南よりの強風を春一番〔はるいちばん〕と呼びます。
○夏至
二十四節気の1つで、一年で最も昼の時間が長くなる日です。それは、太陽が最も北(北回帰線の真上)に来るために起こる現象です。しかし実際は夏至は梅雨の真っ只中なので、日照時間は冬よりも短いことが多いようです。6月21日頃。
一年で一番昼の時間が長い日
夏至とは、この日を過ぎると本格的な夏が始まると意味です。
冬至にかぼちゃを食べるように、この日も何かを食べる習慣がありますが、何を食べるかは地方によってまちまちです。例えば関西地方では、タコの八本足のようにイネが深く根を張ることを祈願してタコを食べます。
太陽の化身 天照大身神
古来、天照大神〔あまてらすおおみかみ〕は太陽の化身と位置づけされていました。日本各地にある古代遺跡や書籍などから、その信仰を垣間見ることが出来ます。
「夏至」という言葉が入って来たのは、中世になって中国から二十四節気が入ってきてからのようです。
その後、各地で太陽の生命力を得るために夏至の日を祝うお祭りが開催されるようになりました。
2003年から、夏至の日は昼の時間が長いので「電気を消してスローな夜を」というタイトルで節電を呼びかけるイベントが行われています。
○秋分
毎年9月23日頃を秋分の日と言い「祖先を敬い、亡くなった人をしのぶ日」として1948年に法律で制定されました。
また秋分の日は、祝日法の上で「秋分日」とされています。毎年2月1日に、国立天文台が作成する「暦象年表」という小冊子に基づき閣議で来年の(秋分の日の)日にちが決定されます。
祖先を供養する日
秋分の日は春分の日と同様に、昼と夜の長さが等しくなる日です。しかし、春分の日よりも昼の平均気温は10度程高く、まだ夏の気配が残ります。
秋分の日を中心とした一週間を「秋彼岸〔あきひがん〕」と言います。各家々では、家族そろってお墓参りに行ったり、祖先を供養する「法会〔ほうえ〕」が行われたりします。
自然信仰から生まれた祖先供養の日
元々農村部では、春分の頃に豊作を祈り、秋分の頃に豊作を祝う自然信仰があり、山の神様である祖先の霊を春分以前に山から里に迎え、秋分以降に里から山へ送る儀式が行われていました。しかし、仏教の浸透とともに秋分は「秋の彼岸」として祖先を供養する意味を持ち始めました。
明治時代に秋分の中日を「秋季皇霊祭〔しゅうきこうれいさい〕」と定め、宮中において祖先をまつる日となった事がきっかけで、一般市民の間でもそのように定着していきました。
1948年には、お寺参りの日・先祖供養の日など、宗教的慣例としてのまつりの日だけではなく、広い意味で「祖先を敬い、亡くなった人を忍ぶ日」として国民の祝日に制定されました。
秋分の日と彼岸
秋分(春分)の3日前の日を「彼岸の入り」といい、3日後を「彼岸の明け」と言い、その7日間を彼岸と言います。秋分・春分はその中間に位置するため「彼岸の中日」と呼ばれています。
また「彼岸」とは元々仏教用語で「煩悩に満ちた世界から解脱した悟りの世界」を指します。これは、簡単に言えば「亡くなった先祖達の霊が住む世界」のことです。その祖先の霊を供養するために、私たちはお彼岸になると「お墓参り」へ行きます。
○冬至
毎年12月22日頃に、一年で最も夜の長さが長くなる日があり、これを冬至と言います。昔は冬至の日は「死に一番近い日」と言われており、その厄〔やく〕を払うために体を温め、無病息災を祈っていました。この慣わしは現在も続いています。
一年で最も夜の長い日
冬は植物が枯れ、動物は冬眠してしまうため、食料が手に入りにくくなります。更に日照時間が短いため生命の源である太陽の恵みを享受することが出来にくく、人々は生活の不安を感じていました。特に北半球では、冬至に対する不安は大きかったようです。そこで無病息災を祈るために、野菜の少ない季節に栄養を補給するためのかぼちゃを食べたり、その香りに邪を祓う霊力があると信じられている柚子のお風呂に入るなどして夜を越していたようです。
冬至は「とうじ」と読みますが、これを「湯治〔とうじ〕」とかけて生まれたのが柚子湯(柚子を入れたお風呂)です。柚自体にも意味があり、「融通〔ゆうずう〕が利きますように」という願いが込められているそうです。
冬至は分岐点
古来、冬至は新年の起点として考えられていました。というのも、冬至は一年で最も日が短く、この日を境に昼間の時間が延びていくからです。また、昼は長くなってはゆきますが、寒さは一段と厳しくなります。
中国の太陰暦で冬至は暦の起点とされ、厳粛な儀式を行っていました。日本には中世になって伝わり、宮中などで朔旦冬至〔さくたんとうじ〕という祝宴を催していたようです。
生命の終わる冬を乗り切る為に
冬至は生命の終わる時期だと考え、そしてそれを乗り越えるため無病息災の祈願などをし不安を取り除こうとしました。その時に食べる食物の1つがかぼちゃです。
昔は夏に収穫したものを冬至まで大切に保存しておいていましたが、現在では夏に南半球で生産された旬の輸入かぼちゃを食べることが一般的です。冬至かぼちゃが有名なので、冬の野菜だと思っている人も多いのではないでしょうか。
また、柚子には血行を促進する成分や、鎮痛作用のある成分が含まれています。更にビタミンCも豊富なため、湯につかり全身からそれらの成分を吸収することで風邪をひきにくくする効果があります。
○五節句
五節句の「節」というのは、唐時代の中国の暦法で定められた季節の変わり目のことです。暦の中で奇数の重なる日を取り出して(奇数(陽)が重なると陰になるとして、それを避けるための避邪〔ひじゃ〕の行事が行われたことから)、季節の旬の植物から生命力をもらい邪気を祓うという目的から始まりました。この中国の暦法と、日本の農耕を行う人々の風習が合わさり、定められた日に宮中で邪気を祓う宴会が催されるようになり「節句」といわれるようになったそうです。
五節句には、3月3日、5月5日のように奇数の重なる日が選ばれていますが、1月だけは1日(元旦)を別格とし、7日の人日(じんじつ)を五節句の中に取り入れています。
「五節句」の制度は明治6年に廃止されましたが、今での年中行事の一環として定着しています。
○人日の節句
「人日」とは五節句の1番目の節句で、陰暦1月7日のことをいいます。お正月最後のこの日は、七草粥を食べて1年の豊作と無病息災を願います。
旬の生き生きした植物である七草を粥にして食べれば、自然界から新たな生命力をもらえ、無病息災で長生きができるとされていました。かつては、前日に野山で菜を摘み、年棚(歳神を祭った棚)の前で七草囃子(ななくさばやし)を唄いながらすりこ木でたたいたそうです。こうすることで、七草の力をさらに引き出すことができると考えられてました。
このように丁寧に細かく刻まれた七草粥は、正月のご馳走に疲れた胃腸をいたわり、ビタミンを補う効果もあります。
若菜摘みから始まった風習
日本には古くから年の初めに雪の間から芽を出した若菜を摘む、「若菜摘み」という風習がありました。
また「若菜摘み」とは関係なく、平安時代には、中国の年中行事である「人日」(人を殺さない日)に作られる「七種菜羹〔ななしゅさいのかん〕(7種類の菜が入った吸い物)」の影響を受けて、7種類の穀物で使った塩味の利いた「七種粥」が食べられようになったそうです。 その後、「七種粥」は「若菜摘み」と結びつき、7種類の若菜を入れた「七草粥」になったと考えられます。
江戸時代には幕府が公式行事として「人日」を祝日にしたことで、「七草粥」を食べる風習が一般の人々にも定着していったようです。
七草粥の作り方
地方によって、多少異なりますが現在スーパー等で販売されている七草は、セリ・ナズナ・ハコベラ・ホトケノザ・ゴギョウ・スズナ・スズシロが一般的です。
七草粥の作法は少し変わっており、「七草なずな、唐土の鳥が日本の土地に渡らぬ先に…」と、七草囃子を唄いながら、まな板に乗せた七草をすりこ木や包丁でたたきます。
米は4・5倍のお水に30分間浸し、強火にかけます。吹いてきたら弱火にし、2~30分炊き、火を止める直前に刻んだ七草を入れ、塩で味をつけて完成です。
○上巳の節句(じょうし)
「上巳」は3月3日にあたり、桃が咲く時期と重なることから「桃の節句」とも言われ、桃などの自然の生命力をもらうなどして厄災を祓います。 また最近では、女の子の誕生と成長を祝う「雛祭り」として一般に浸透しています。
健康を祈って災厄を祓う農村儀礼
元々3月3日は、年齢・性別関係なく、草や藁〔わら〕で作った人形〔ひとがた〕の体を撫で穢れ〔けがれ〕を移し、健康を祈って災厄を祓うことを目的とした農村儀礼が行われていました。また、平安貴族の10歳くらいまでの子女は、人形〔ひとがた〕を貴族の日常生活を真似たごっこ遊びをする目的に用いていたようです(この遊びが後にひな祭りになりました)。
上巳の節句と雛祭りの関係
平安時代頃から、3月の初めに海や山へ出て一日を過ごし身の穢れを洗い流す農村儀礼がありました。田植えの始まりにあたるこの時、田の神を迎える為に、紙で作った人形で体を撫でて穢れを落とした後、海や川に流していたようです。また、桃が邪気を祓い長寿を保つと言う中国思想の影響を受けて、桃の花の入った桃酒を飲むようになったようです。
江戸時代に入ると、紙の雛人形を流す行事は川が汚れるという理由から流すことが難しくなってきました。その頃から、現在の雛壇を飾る「雛祭り」へと行事の内容が移行したのではないかと言われています。
○端午の節句
「端午の節句」は5月5日にあたり、「菖蒲〔しょうぶ〕の節句」とも言われます。強い香気で厄を祓う菖蒲やよもぎを軒(のき)につるし、また菖蒲湯に入ることで無病息災を願いました。
また、「菖蒲」を「尚武〔しょうぶ〕」という言葉にかけて、勇ましい飾りをして男の子の誕生と成長を祝う「尚武の節句」でもあります。
立身出世を願う男の子の節句
江戸以降は男子の節句とされ、身を守る「鎧」や「兜」を飾り、「こいのぼり(※)」を立てて男子の成長や立身出世を願ってお祝いをします。また、初節句(男の子が生まれて初めての節句)にはちまきを、2年目からは新しい芽がでるまで古い葉を落とさない事から「家督が途絶えない」縁起物として「柏餅」を食べます。
地方によっては、子供の行事としてだけでなく、田の神を迎えるための禊の名残として菖蒲湯に入る習慣も残っているようです。
登竜という激流(登竜門)を鯉が登ったという中国の伝説を受け、鯉には出世と健やかな成長を願う親の気持ちが託されています。
男の子の成長を祈るまつりへと変化
端午の節句は奈良時代から続く古い行事です。もとは月の端〔はじめ〕の午〔うま〕の日という意味で、5月に限ったものではありませんでした。しかし、午〔ご〕と五〔ご〕の音が同じなので、毎月5日を指すようになり、やがて5月5日のことになったとも伝えられます。
当時は邪気を避け魔物を祓う薬草とされていた「菖蒲」を、よもぎと共に軒にさし、あるいは湯に入れて「菖蒲湯」として浴しました。
時代が武家社会に移るにつれ、これまでの風習が廃れ、代わりに「菖蒲」と「尚武」をかけた尚武(武士を尊ぶ)の節句へと移っていきます。この流れを受け、江戸時代には徳川幕府の重要な式日が5月5日と定められ、大名や旗本が式服で江戸城に参り、将軍にお祝いを奉じるようになりました。また、将軍に男の子が生まれると、玄関前に馬印〔うましるし〕や幟〔のぼり〕を立てて祝いました。こうして時代と共に男の子の誕生と成長を祝うお祭りへとなっていきました。
現代の端午の節句
男の節句とされていたので昔は鎧や兜はお父さんやおじいちゃんが飾るのが習わしでしたが、現在では特にこだわる必要はないそうです。4月中旬までには飾りの準備を終わらせ、当日か前日の晩には両家両親や知人を招き、縁起物のご馳走でもてなします。 また、今でも「強い香気による厄払い」という意味が込められた「菖蒲湯」には性別年齢関係なく入浴しています。
○七夕の節句
七夕〔たなばた〕とは「7月7日の夕方」を意味しています。七夕行事は、中国に古くから伝わる牽牛・織女星の伝説から発達した乞巧奠〔きこうでん〕の行事に、日本古来の棚機津女〔たなばたなつめ〕の信仰が混ざり合って形成されたものでした。
織姫と彦星が逢瀬を重ねる日
7月7日は、織姫と彦星が逢瀬を重ねるのを星を見守る日として知られています。この日、芸技が上達するように、出会いがありますようにという願いを詩歌にした短冊を竿竹にくくりつけると祈りが届くとされています。
また、この時期はお盆(旧7月15日)を迎えるための準備(七夕盆)としての意味をもち、畑作の収穫祭を祝う祭りが人々の間で行われていました。この時、健康を祈り素麺の元となったお菓子「索餅〔さくべい〕」が食べられていました。索餅は熱病を流行らせた霊鬼神が子供時代好きな料理で祟りを沈めるとされていました。やがて、索餅は舌触りのよい素麺へと変化し、七夕に素麺を食べるようになったそうです。
七夕と機織娘
日本では古来より、「棚機つ女」といわれる女性が、機〔はた〕で織った布を神におさめ、病気や災厄が起こらないように願ったという話がありました。7月7日〔しちせき〕を「たなばた」と呼ぶのは、この「棚機つ女」がもとになっています。
そして、中国の文化に強く影響を受けた平安貴族たちは、竹竿に糸をかけて願いを星に祈るとかなえられるという乞巧奠の習わしに従い梶の葉に歌を書き付けて手向ける「星祭り」を行うようになりました。
その後、乞巧奠が大衆の間にも広まり、やがて棚機つ女と結びつき現在のように7月7日の七夕となっていったようです。
江戸時代に入ると、短冊に詩歌を書き、笹竹に軒先に立てる風習が寺子屋の普及とともに浸透していきました。明治になり、各地の商店街などで大規模な七夕祭りが開かれるようになり、さらに一般の人々の風習として広まっていったようです。
○重陽の節句
「重陽」とは9月9日にあたり、菊に長寿を祈る日です。陽(奇数)が重なる日そして、奇数の中でも一番大きな数字という意味で重陽といわれています。日本では奈良時代から宮中や寺院で菊を観賞する宴が行われています。
邪気を祓い長生き効果のある菊
古代中国では菊は「翁草〔おきなくさ〕」「千代見草〔ちよみくさ〕」「齢草〔よわいくさ〕」と言われ、邪気を祓い長生きする効能があると信じられていました。
その中国の影響を受けて日本では、8日の夜に菊に綿をかぶせ、9日に露で湿ったその綿で体を拭いて長寿を祈っていました。また、菊に関する歌合わせや菊を鑑賞する宴が催されていたそうです。現在は寺社などで行事を行う程度で一般にこれといった行事はあまり行われていないようです。
秋の収穫祭が起源?
平安時代以前は、農山村や庶民の間で秋の田畑の収穫が行われる時期に「栗の節句」とも呼ばれて栗ご飯などで節句を祝いました。(その後も農民の間では収穫祭の意味合いが強く受け継がれていきました)
平安時代に入って中国思想の影響を受けると、菊の花を浸した「菊酒」を飲み交わし、茱萸(しゅゆ=ぐみの実のこと)を掛けて悪気を祓う菊花の宴が催されるようになりました。また、菊に関する歌合せや、「菊合わせ」という現代で言う菊のコンクールが盛んに行われるようになりました。
現在でも、9日に行われるとは限りませんが、菊のコンクールや鑑賞を行う風俗は残っています。
無病息災のための神事
京都の上賀茂神社では、無病息災を祈る重陽の節会が現在でも行われています。
9日には、境内細殿前の土俵の左右から、弓矢を手にした二人の刀弥〔とね〕が横とびしながら2つの立砂の前へと現れ、「カーカーカー」「コーコーコー」と烏の鳴きまねをした後、近所の子供が相撲を行う烏相撲〔からすすもう〕や、「菊の被綿〔きせわた〕」の神事がとりおこなわれます。